2023年11月30日
前回ブログ 「食事が楽しくなる日本の食物史」 を混種加筆しました。
前回ブログ「食事が楽しくなる日本の食物史」に、今週はちょこちょこ加筆修正しました。
先週の最初の分をお読みの方で興味がある方は、ぜひご覧ください。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
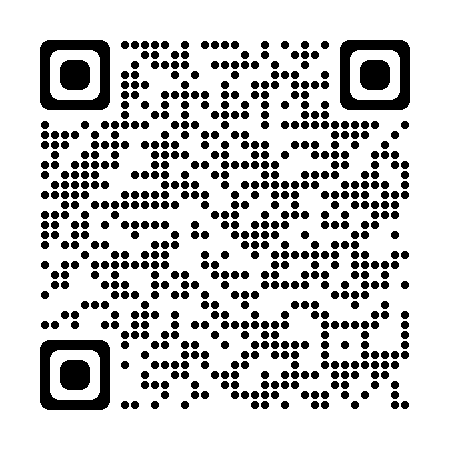
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
先週の最初の分をお読みの方で興味がある方は、ぜひご覧ください。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
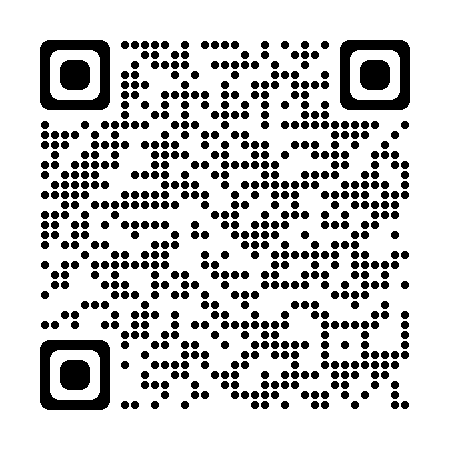
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
Posted by ansei at
22:34
│Comments(0)
2023年11月20日
食事が楽しくなる日本の食物史・改善しやすくなる

買う食べ物の産地物語が頭に浮かび、楽しくなる。
「日本の食物史」を書いてから、スーパーの食料品売り場やレストラン等を利用することが前より楽しくなりました。今まで、いつ、どこから、どんな経緯で日本の店先に並ぶようになったか等の背景や物語を考えたこともなかったからです。
レストランの言葉はほとんど外来語
「日本の食物史」を書くことで、食品を買わなくても見るだけで、そのいわれが頭に浮かぶようになったからです。
レストラン等の飲食店に行けば用語が元は何語で、コック・テーブル・コーヒー・スープ等は鎖国中オランダ船が長崎に来ていたころの名残とか、パン・カステラ・金平糖を見たら戦国時代(1500年代)宣教師ルイスフロイス等ポルトガル船が来ていたころの名残とか、頭に浮かぶようになりました。
子どもの頃から食べている食物だから当たり前ではない。食を改善しやすくなる。
縄文・弥生時代~江戸時代・明治維新と、日本人が食べているものが変化していることを知れば、こういう理由で、今、私はこの食物を食べるようになったのかが分かり、子どもの頃から当たり前に食べていたものが当たり前ではないことが分かります。
リウマチ膠原病に良い食物悪い食物を考えて、食事を改善したいと思っていても、子どもの頃から食べているから切り替えられないという人もいます。
人によって良い悪いがあるでしょうが、膠原病の元学校の先生で牛乳パンのパターンを変えられない人がいました。学校給食で栄養が良いと思って食べていたからでしょうか。しかしながら、日本の食物史を知れば、今食べられている理由が分かります。頭が切り替わり食事の改善がしやすくなると思います。
黄色のスイカを見たら、以前は改良品と思って見ていましたが、今は原種が原産国南アフリカで育っていた頃の色だと思うようになりました。留学生に聞くと、現在世界中が赤いスイカのようです。スイカは赤いのが当たり前と思っていたら、改良品で当たり前といえるかどうか分からなくなってきます。
健康を左右する食物の発明
今年は、俳優で歌手の渡辺徹さんが亡くなったのですが、今まで肥満が原因の病気をいろいろ発症されています。妻の歌手榊原郁恵さんもいろいろ献身されたと思います。しかし、タレント仲間の話では、何を食べるにもマヨネーズが大好きで何にでもかけて食べていたそうです。
私は、それが若くして亡くなった原因ではないかと思っています。
話が面白く人柄もいい人だったので残念なことでした。
マヨネーズは、スペイン領のミノルカ島の一主婦が考案した食品です。マヨネーズは、油と酢を混ぜたものでほとんど油です。世の中にマヨネーズがなかったら、もっと長生きしたかもしれません。
マヨネーズはマヨたこ・お好み焼・サラダ等に使われ、キューピーマヨネーズ等の企業ができるほどの産業となっています。マヨネーズを発明したミノルカ島の一主婦は儲かったのでしょうか。
食べ物ができた物語は面白い
江戸時代に「たい焼」ができた背景を、当HP「日本の食物史」に書きました。そして「たい焼」と名づけたのが良かったと書きました。
最近放送された福岡RKBのラジオ番組「Toi toi toi(トイ トイ トイ)」の「今日の朝まめ」の話では、「初め亀焼という名前で売り出したら売れなかった」そうです。しかし、亀は「鶴は千年、亀は万年」と健康長寿につながり、亀甲紋は縁起が良い紋です。
「たい焼」と名づけた江戸時代の人は、いずれにしろ「縁起のいい名前をつけたかった」のではないか、と思ったのでした。
ネーミングは大事ですね。
まだ当HPの「日本の食物史」を見ていない方は、ご覧になると食物の見方が変わると思います。
今より食物に興味が湧き、食事が楽しくなると思います。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
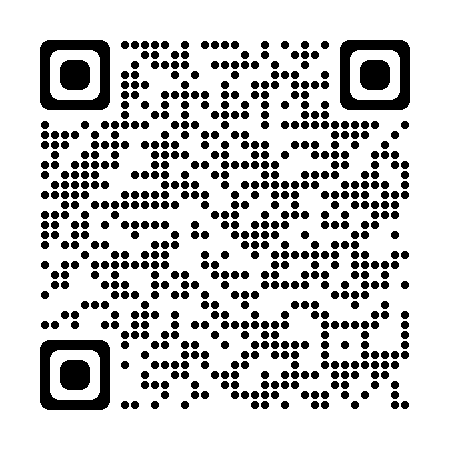
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
Posted by ansei at
21:53
│Comments(0)
2023年11月09日
現代人は薬・病院しか頭に浮かばない。東洋医学の長所と効果を国は隠す!
現代人は薬・病院しか頭に浮かばない。東洋医学の長所と効果を国は隠す!
西洋医学・東洋医学の違い・特長!優劣はなく併用や使い分けていい!
世界各国には、体の不調を治す民間療法がそれぞれ受け継がれています。
西洋医学の特長はエビデンスがあり、民間療法にはそれがないと世間では言われています。そして、西洋医学は、血液検査等のデータを基に診断し、投薬治療等を行います。スグ効く反面、副作用や体を傷つける側面があります。対症療法です。
一見科学的で信頼があるように思えます。しかし、そこには患者の生活や体質、自然治癒力等を見ていない狭い視野等が見てとれます。
東洋医学と日本の民間療法の特長は同じです。当HP「日本の食物史」や「国宝医心方(古代医学)」のページを見た人は分かると思います。
今から中国伝統医薬学(中医学・東洋医学・薬膳)の歴史をたどります。すると、ある面、東洋医学の優れている面に気づくと思います。
◦紀元前2100~1500年の夏の時代に酒が造られ始め、梅酒等の薬酒につながりました。
◦紀元前1700~1100年の商(殷)の時代に料理人伊尹(いいん)がスープから中薬(※)を煎じる方法を考案しました。「湯液経」という本を記したと言われています。
※中薬とは、効能が認められる自然界の植物・動物・鉱物・海産物をいう。日本では生薬のこと。
鉱物(ミネラル補給・温泉)でリウマチ膠原病が、ワカメでアトピーが治った例があります。
◦紀元前1066~771年西周の時代には飲食と医療の職が創設されました。
包人、膳夫、王様の栄養管理・味の配合等を管理する役目の食医、主に医療法律や対策の
管理職の医師・今の耳鼻科眼科内科を含めた医師の疾医・今の皮膚科整形外科を含めた医師の
瘍医・獣医等がありました。
この頃から、酢・味噌・醤油等の製造が始まりました。
◦紀元前770~221頃の春秋戦国時代に、中国伝統医薬学(中医学)の理論体系を確立した「黄帝内経」が書かれました。そこには、自然界・季節・飲食・生活と人の健康を結びつけて考えられています。
また、人体の生理・解剖・病理(原因等)・診断治療に至るまで書かれています。
◦紀元前202年~220年の漢の時代には、最初の薬学専門書「神農本草経」全3巻が書かれました。365種類の食材・中薬を上品・中品・下品に分けて説明しています。
上品は、毒性がなく多量に長く食べられる長寿に効果があるもの。
中品は、毒性があるものとないものがあって、病気を予防し虚弱を補うもの。
下品は、毒性があり長く服用できないもの
です。
漢の時代には、中国伝統医薬学の臨床(診察治療)を確立した「傷寒雑病論」が張仲景によって書かれました。その後、「傷寒論」と「金匱要略方論」の2冊になりました。
「傷寒論」には、113の方剤が記されています。
方剤とは、いくつかの中薬を組み合わせたもので、日本の漢方薬にあたるものです。その中には今も使われている「葛根湯」や冬カゼの治療方剤「桂枝湯」(桂枝・芍薬・甘草・生姜・大棗)があります。ほとんどが食材で構成され、食材の薬効が認められていたのです。
「傷寒雑病論」には、処方だけでなく飲み方も記されています。
例えば、方剤を飲んでしばらくたった後に温かいおかゆを飲ませれば薬効が高まる等です。
そして、面白いのは食物の注意事項が、当HP「感染症対策」の古代医学の「医心方」と
当HP「コロナ・インフルエンザ対策」のAI解析の感染しやすい人・重症化しやすい人の食物とほとんど同じということです。
「傷寒雑病論」は、中国伝統医薬学(東洋医学)の診断法の病気の症状を集めて判断する原点になりました。
「西洋医学」は検査結果だけで判断治療しますが、「東洋医学」では病気の人の多様な背景を考えて診断治療します。前者は副作用が必ずあり、後者は主に食物を使うので副作用がほとんどないということです。
また、西洋医学は、統計データは何百何千何万人という人数、しかも、薬品会社が捏造したデータです。東洋医学は、何千年も何万人以上に実際使われて発展してきたものです。迷信ではないと思うのです。
東西の医学は使い分けしたり併用してもいいと思うのです。現代中国医療は両方発展し併用しているのです。
日本の場合、以前ブログに書いたイギリス等諸外国に比べ、西洋医学に偏りすぎているといえるのです。
日米の薬の利権のため情報を出さない。東洋医学・民間療法も探してみる!
明治維新で東洋医学が禁止されて以来、西洋医学以外の治し方の地位が世界に比べ低くなったのです。
また、米国・日本の薬の利権のため国がそうさせているのです。
今までのように、東洋医学とその流れにある民間療法は決して迷信ではないと思うのです。西洋医学・東洋医学を一緒に上手く利用していいのではないでしょうか。
病院以外の薬を使わない治し方も探してみましょう。
当方では、そのような実績のある方法を教えています。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
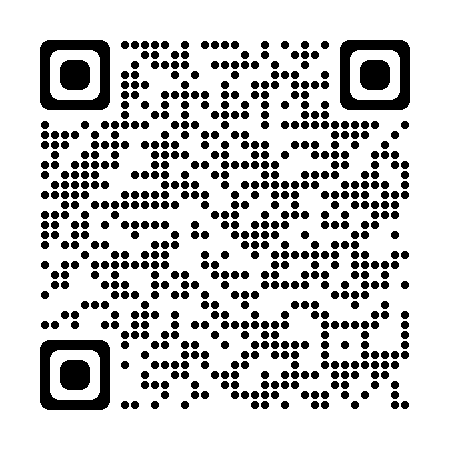
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
西洋医学・東洋医学の違い・特長!優劣はなく併用や使い分けていい!
世界各国には、体の不調を治す民間療法がそれぞれ受け継がれています。
西洋医学の特長はエビデンスがあり、民間療法にはそれがないと世間では言われています。そして、西洋医学は、血液検査等のデータを基に診断し、投薬治療等を行います。スグ効く反面、副作用や体を傷つける側面があります。対症療法です。
一見科学的で信頼があるように思えます。しかし、そこには患者の生活や体質、自然治癒力等を見ていない狭い視野等が見てとれます。
東洋医学と日本の民間療法の特長は同じです。当HP「日本の食物史」や「国宝医心方(古代医学)」のページを見た人は分かると思います。
今から中国伝統医薬学(中医学・東洋医学・薬膳)の歴史をたどります。すると、ある面、東洋医学の優れている面に気づくと思います。
◦紀元前2100~1500年の夏の時代に酒が造られ始め、梅酒等の薬酒につながりました。
◦紀元前1700~1100年の商(殷)の時代に料理人伊尹(いいん)がスープから中薬(※)を煎じる方法を考案しました。「湯液経」という本を記したと言われています。
※中薬とは、効能が認められる自然界の植物・動物・鉱物・海産物をいう。日本では生薬のこと。
鉱物(ミネラル補給・温泉)でリウマチ膠原病が、ワカメでアトピーが治った例があります。
◦紀元前1066~771年西周の時代には飲食と医療の職が創設されました。
包人、膳夫、王様の栄養管理・味の配合等を管理する役目の食医、主に医療法律や対策の
管理職の医師・今の耳鼻科眼科内科を含めた医師の疾医・今の皮膚科整形外科を含めた医師の
瘍医・獣医等がありました。
この頃から、酢・味噌・醤油等の製造が始まりました。
◦紀元前770~221頃の春秋戦国時代に、中国伝統医薬学(中医学)の理論体系を確立した「黄帝内経」が書かれました。そこには、自然界・季節・飲食・生活と人の健康を結びつけて考えられています。
また、人体の生理・解剖・病理(原因等)・診断治療に至るまで書かれています。
◦紀元前202年~220年の漢の時代には、最初の薬学専門書「神農本草経」全3巻が書かれました。365種類の食材・中薬を上品・中品・下品に分けて説明しています。
上品は、毒性がなく多量に長く食べられる長寿に効果があるもの。
中品は、毒性があるものとないものがあって、病気を予防し虚弱を補うもの。
下品は、毒性があり長く服用できないもの
です。
漢の時代には、中国伝統医薬学の臨床(診察治療)を確立した「傷寒雑病論」が張仲景によって書かれました。その後、「傷寒論」と「金匱要略方論」の2冊になりました。
「傷寒論」には、113の方剤が記されています。
方剤とは、いくつかの中薬を組み合わせたもので、日本の漢方薬にあたるものです。その中には今も使われている「葛根湯」や冬カゼの治療方剤「桂枝湯」(桂枝・芍薬・甘草・生姜・大棗)があります。ほとんどが食材で構成され、食材の薬効が認められていたのです。
「傷寒雑病論」には、処方だけでなく飲み方も記されています。
例えば、方剤を飲んでしばらくたった後に温かいおかゆを飲ませれば薬効が高まる等です。
そして、面白いのは食物の注意事項が、当HP「感染症対策」の古代医学の「医心方」と
当HP「コロナ・インフルエンザ対策」のAI解析の感染しやすい人・重症化しやすい人の食物とほとんど同じということです。
「傷寒雑病論」は、中国伝統医薬学(東洋医学)の診断法の病気の症状を集めて判断する原点になりました。
「西洋医学」は検査結果だけで判断治療しますが、「東洋医学」では病気の人の多様な背景を考えて診断治療します。前者は副作用が必ずあり、後者は主に食物を使うので副作用がほとんどないということです。
また、西洋医学は、統計データは何百何千何万人という人数、しかも、薬品会社が捏造したデータです。東洋医学は、何千年も何万人以上に実際使われて発展してきたものです。迷信ではないと思うのです。
東西の医学は使い分けしたり併用してもいいと思うのです。現代中国医療は両方発展し併用しているのです。
日本の場合、以前ブログに書いたイギリス等諸外国に比べ、西洋医学に偏りすぎているといえるのです。
日米の薬の利権のため情報を出さない。東洋医学・民間療法も探してみる!
明治維新で東洋医学が禁止されて以来、西洋医学以外の治し方の地位が世界に比べ低くなったのです。
また、米国・日本の薬の利権のため国がそうさせているのです。
今までのように、東洋医学とその流れにある民間療法は決して迷信ではないと思うのです。西洋医学・東洋医学を一緒に上手く利用していいのではないでしょうか。
病院以外の薬を使わない治し方も探してみましょう。
当方では、そのような実績のある方法を教えています。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
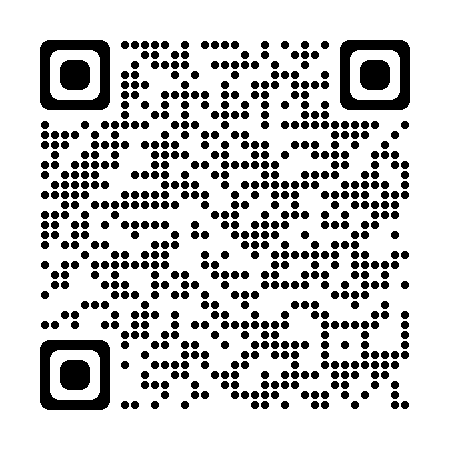
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
Posted by ansei at
15:16
│Comments(0)
2023年11月03日
現代・病院・病院しか頭に浮かばない。昭和までは別の選択があった。
現代人は薬・病院しか頭に浮かばない。昭和までは別の選択があった。
現代人は薬・病院しか頭に浮かばないようになった。
週刊誌の編集者さえ、薬・解熱剤しか頭に浮かばないようになったのは衝撃でした。
10月の「女性自身」に、大筋の話として、コロナ・インフルエンザ対策に解熱剤を使う時に食べ合わせにより害が生じることがあるので注意するように、という内容の記事がありました。
そもそも、コロナ・インフルエンザの熱症状はウィルスを減少させるための人の体の免疫反応です。それゆえ、解熱剤・総合感冒薬で熱を下げると、重症化したりカゼが長引いたりします。 氷で冷やすとスグ止められるので良いのです。
※当HP「症状を楽にする方法」を参照
https://ryumachi.ansei-support.com/yobo/
昔、スペインカゼで死亡者が多かったのは、解熱剤アスピリンを使ったからです。それ以来、カゼに解熱剤を使わないのが医学界の常識になったのです。解熱剤はよほどの時に病院で相談した方がよろしいでしょう。
医薬品・業界との利害関係から、マスコミ(広告)やマスコミ名医がそれを言わないので、解熱剤が市場に足りないニュースが流れるのです。
昭和まで西洋医学以外を使っていた理由
当HPの「日本の食物史」を見た人は分かると思います。
おさらいしますと、奈良・平安時代に中国の禅寺から仏教が伝来しました。この頃は、中国の伝統医薬学(東洋医学)・薬膳が運よくできあがっていた頃です。昔の僧侶は文化医学を教えていました。仏教の伝来というのは中国の禅の文化医学が伝来したということです。
精進料理は中国の健康食です。それ以来、日本人は仏教思想と精進料理を基本として、江戸時代まで生きてきました。それを元にして和食というようになりました。また、それまで中国から伝来した食物は、薬として伝来したものが多いのです。
お茶や梅(干)・味噌はその代表で、今も使われています。今でも健康に良いといわれているのは当然のことでしょう。当HP「新型コロナ・インフルエンザの治し方」に書いているように、梅干しは江戸時代にコレラ患者の命を救ったのです。ワクチン・薬を使っていません。
以上のように、病院に行かなくとも食物等の自然療法で自分の病気を治す術を、江戸時代まで身につけていたのです。
それが、明治維新で仏教を否定し寺・僧侶を排斥したり、東洋医学・民間療法を禁止したりしました。そして、食文化も西洋化したのです。しかし、個人の知恵として精進料理やお茶・梅干し・お灸等の民間療法は昭和まで残りました。
今の日本人は病院・薬しか頭に浮かばないようにさせられている!
明治時代~昭和まで、庶民には仏教の文化医療は残りましたが、食の洋風化の波は強くなり、今では仏教の医療の知恵・民間療法・食事は頭に浮かばなくなったのです。
昭和50年代頃の食事が健康に良い食事といわれています。
よく考えると、明治の人の親は江戸時代生まれで、昭和の人の親は明治・大正生まれです。そのことから、昭和までは健康食・民間療法が残っています。病院・薬を利用しなくてもいい知恵・食品が一家にひとつはありました。世界各国には、今も伝統の知恵が残っています。
昭和では三世代同居から核家族になり、現在は、家族が一緒にではなく別々に食事をするようになりました。これでは健康の知恵が途絶えるはずです。
それと、国・役所がいまだに西洋医学以外の民間療法の効果をうたったら取り締まることです。治ったのが本当でもチラシを回収させます。ネット広告に文句を言ってきます。
チラシにも、本当ならば治った人が「このお茶を飲んでガンが治りました」「リウマチ膠原病が治りました」と言っていいのです。役所と裁判したら役所が負けます。今まで全敗です。表現の自由が勝つのです。
健康誌「壮快」の中身の変化はひどいものです。昔の「壮快」は、健康食品や食物の知恵で治った記事の後に、その健康食品の購入方法が書いてありました。しかし、時が経つほど年々役所に締めつけられました。現在、購入方法が載っていません。
あと、マスコミも役所の指示に従って、東洋医学・民間療法を取り上げないので問題があります。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
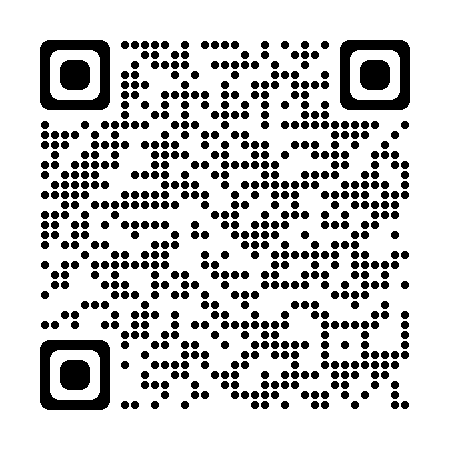
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
現代人は薬・病院しか頭に浮かばないようになった。
週刊誌の編集者さえ、薬・解熱剤しか頭に浮かばないようになったのは衝撃でした。
10月の「女性自身」に、大筋の話として、コロナ・インフルエンザ対策に解熱剤を使う時に食べ合わせにより害が生じることがあるので注意するように、という内容の記事がありました。
そもそも、コロナ・インフルエンザの熱症状はウィルスを減少させるための人の体の免疫反応です。それゆえ、解熱剤・総合感冒薬で熱を下げると、重症化したりカゼが長引いたりします。 氷で冷やすとスグ止められるので良いのです。
※当HP「症状を楽にする方法」を参照
https://ryumachi.ansei-support.com/yobo/
昔、スペインカゼで死亡者が多かったのは、解熱剤アスピリンを使ったからです。それ以来、カゼに解熱剤を使わないのが医学界の常識になったのです。解熱剤はよほどの時に病院で相談した方がよろしいでしょう。
医薬品・業界との利害関係から、マスコミ(広告)やマスコミ名医がそれを言わないので、解熱剤が市場に足りないニュースが流れるのです。
昭和まで西洋医学以外を使っていた理由
当HPの「日本の食物史」を見た人は分かると思います。
おさらいしますと、奈良・平安時代に中国の禅寺から仏教が伝来しました。この頃は、中国の伝統医薬学(東洋医学)・薬膳が運よくできあがっていた頃です。昔の僧侶は文化医学を教えていました。仏教の伝来というのは中国の禅の文化医学が伝来したということです。
精進料理は中国の健康食です。それ以来、日本人は仏教思想と精進料理を基本として、江戸時代まで生きてきました。それを元にして和食というようになりました。また、それまで中国から伝来した食物は、薬として伝来したものが多いのです。
お茶や梅(干)・味噌はその代表で、今も使われています。今でも健康に良いといわれているのは当然のことでしょう。当HP「新型コロナ・インフルエンザの治し方」に書いているように、梅干しは江戸時代にコレラ患者の命を救ったのです。ワクチン・薬を使っていません。
以上のように、病院に行かなくとも食物等の自然療法で自分の病気を治す術を、江戸時代まで身につけていたのです。
それが、明治維新で仏教を否定し寺・僧侶を排斥したり、東洋医学・民間療法を禁止したりしました。そして、食文化も西洋化したのです。しかし、個人の知恵として精進料理やお茶・梅干し・お灸等の民間療法は昭和まで残りました。
今の日本人は病院・薬しか頭に浮かばないようにさせられている!
明治時代~昭和まで、庶民には仏教の文化医療は残りましたが、食の洋風化の波は強くなり、今では仏教の医療の知恵・民間療法・食事は頭に浮かばなくなったのです。
昭和50年代頃の食事が健康に良い食事といわれています。
よく考えると、明治の人の親は江戸時代生まれで、昭和の人の親は明治・大正生まれです。そのことから、昭和までは健康食・民間療法が残っています。病院・薬を利用しなくてもいい知恵・食品が一家にひとつはありました。世界各国には、今も伝統の知恵が残っています。
昭和では三世代同居から核家族になり、現在は、家族が一緒にではなく別々に食事をするようになりました。これでは健康の知恵が途絶えるはずです。
それと、国・役所がいまだに西洋医学以外の民間療法の効果をうたったら取り締まることです。治ったのが本当でもチラシを回収させます。ネット広告に文句を言ってきます。
チラシにも、本当ならば治った人が「このお茶を飲んでガンが治りました」「リウマチ膠原病が治りました」と言っていいのです。役所と裁判したら役所が負けます。今まで全敗です。表現の自由が勝つのです。
健康誌「壮快」の中身の変化はひどいものです。昔の「壮快」は、健康食品や食物の知恵で治った記事の後に、その健康食品の購入方法が書いてありました。しかし、時が経つほど年々役所に締めつけられました。現在、購入方法が載っていません。
あと、マスコミも役所の指示に従って、東洋医学・民間療法を取り上げないので問題があります。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
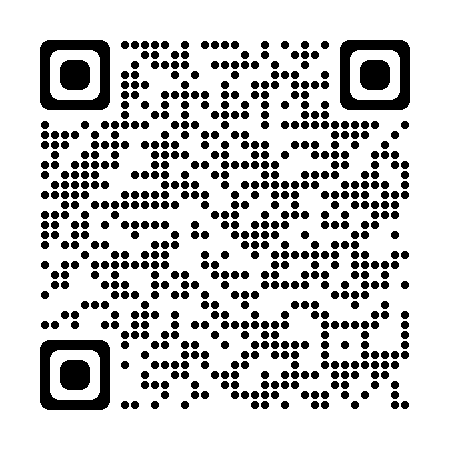
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
Posted by ansei at
18:37
│Comments(0)

