2023年12月07日
リウマチ膠原病治療の効果が出ない・不満な時は観る世界を変える(食事)
【食物はリウマチ膠原病に影響がある。】
食物は、リウマチ膠原病の人にとってほとんど影響していると思われます。
ほとんどの専門医が講演会等でなにを食べても良いと言っていますが、ある食事療法のデータでは、半分治って半分完治までいかないが改善しています。治すためには、100%食事ではないが、ほとんど影響があるということです。
【食事療法にもいろいろある。】
当方のアンケート等の食事の内容では特に悪くないけれど、あまりリウマチ膠原病の改善がみられない場合があります。
また、ご自分の食事で良いことやっているつもりだけど改善しないという人もいるでしょう。
そのような時、打開策はないものでしょうか。世界には食事療法にもいろいろあり、それぞれ違う食事の診断方法と取り組み方があります。
自分の食事のどこが良いか悪いかを、今と別の見方に変えて見直してみると気づくことがあるかもしれません。そのようなことで気づき一つ食物を改善しただけで、症状がみるみる改善した例があります。
【良し悪しでなく薬膳のように食で病気を治そうとする考えがある。】
食事療法には、日本にも世界にもいろいろあります。その一つに、中国伝統医薬学の食療法(薬膳)があります。
薬膳が発展するまでをみて、食物で健康を取り戻そうとする考え方や方法があることを知りましょう。
最も古い食療法の記述は、唐(618~907)の時代、薬王の孫が書いた医学書「備急千金要方」(びきゅうせんきんようほう)に羊・豚・兎の肝臓・胆等を利用して、眼の病気を治療する方法が載っています。現代西洋医学で言うとビタミンAが効くということかもしれません。
同書の「食治篇」には、食物を野菜・果物・穀類・鳥獣虫魚の4つに分類して、それらを使った治し方が載っています。
孫の弟子孟詵は、上記「食治篇」に食材と中薬を増補し、138種の薬膳の処方を編集して初めての食療法の専門書「食療本草」を書きました。
唐の時代、鑑真和上が日本からの熱心な要望を受け、5度の失敗と失明の上来日し、仏教と医学を伝授しました。日本では、奈良時代のことです。
現代人は、何でも薬・病院に頼ることを前ブログにも書きました。
宋の時代(960~1279)に書かれた陳直の「奉親養老書」には、薬を使っても食物をうまく使って治す人には及ばない、という主旨のことが書かれています。
中国最初の中医薬膳学の専門書「飲膳正要」が、金・元時代(1115~1368)に、宮廷医師の忽思慧によって書かれました。
この中で、「飲食五味は五臓を調和する。五臓のバランスが良くなれば、気血(体をめぐる気と血を言う)が充実し精神が元気になる。情緒が安定するため、風邪のように病気の原因になるものが体内に侵入できないので健康になる。」と書かれています。
※五味とは、酸味・甘味・苦味・辛味・鹹味(塩味)のこと
※五臓とは、人体の臓器、肝・心・脾・肺・腎のこと
上記のように、病気を予防し健康を保つためには飲食は大事であるとし、スープ・粥等の多くの料理も紹介しています。
1368~1644の明の時代には薬膳学・中医薬学が発展し、成熟期に入り、有名な李時珍によって「本草綱目」が書かれました。
内容は、食材と中薬を水部・穀部・菜部・菓部・禽部・獣部などに分け、薬・方剤・食薬を使った粥・薬酒等1万以上を載せています。
その中に、食材を用いて病気を治療することと薬膳の内容が多く書かれています。
1644~1912の清の時代に曹慈山が書いた「老老恒言」には、老人のための薬粥100種が書かれています。
また、発熱や発疹・赤痢などの伝染病に関する学問や温病学説が発展しました。
※薬粥は日本の禅寺の健康食になった。
このように、リウマチ膠原病にこの食品は良いか悪いかから一歩踏み出した考え方を持った食事療法があります。
【日本にも世界にもいろいろな食の見方が違う食事療法があります。】
アーユルベーダや国内にもいろいろあります。西洋医学の栄養学もあります。
【悪い食事ではないと思うが、いまいちの時は別の食事療法の見方をしてみる。】
当食事のアンケートを見ても、本人も当方もあまり悪い食事ではないが、いまいちリウマチ膠原病が改善しない時があります。食事だけが発症原因ではないですが、そんな時は今やっている食事療法以外の食事療法の見方からみて、食事の良し悪しが発見できることがあります。
以前、山田まりやさんの本のことをブログで書いたことがあります。何ヶ月かヒマができた山田さんは、マクロビオテックと薬膳を一緒に勉強したのでした。すると、似ているようで違っていることに気づいたようです。
例えば、食物等の陰性陽性の判断が一部違っています。診断の結果が少し違います。したがって、対応策が変わることがあります。
そのようなことがありますので、別の食事療法で観るとヒントになることがあります。
私の例でも、患者の方の現在状況からリウマチが治るはずだと思うのに、何故だろうと思った時、何か他に食べてませんかと言ったら、その患者の方は今まで言ってなかった陰性の食物を思い出し、毎日食べてますと言ったのです。
それを、私は最終的に東洋医学の陰陽等ではなくて、西洋医学のデータに照らし合わせて判断しますと、やはり良くないと判断してその食物を止めてもらったらみるみる好転しました。
また、別の膠原病の方で食のかたよりが一目で分かったので、海藻くらい食べてみませんか、と特に意味もなくつぶやいたのですが、その後、「めかぶ」を食されアトピーが良くなったとことがあります。栄養不足(葉酸)だったかもしれません。
また、食物に対する考え方・食の良い悪い・病気を治すためや体質改善のためと、いろいろな食事療法によって目的・考え方・方法が違うので、違うことをやるのも一つの改善方法です。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
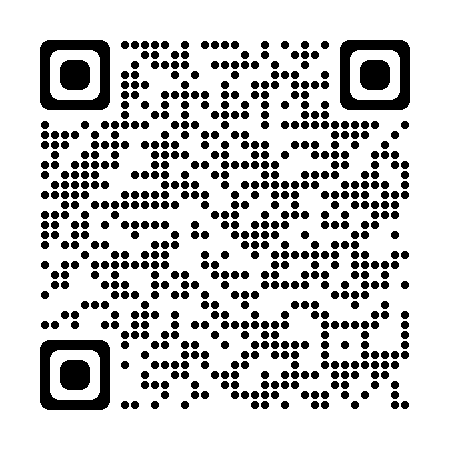
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
食物は、リウマチ膠原病の人にとってほとんど影響していると思われます。
ほとんどの専門医が講演会等でなにを食べても良いと言っていますが、ある食事療法のデータでは、半分治って半分完治までいかないが改善しています。治すためには、100%食事ではないが、ほとんど影響があるということです。
【食事療法にもいろいろある。】
当方のアンケート等の食事の内容では特に悪くないけれど、あまりリウマチ膠原病の改善がみられない場合があります。
また、ご自分の食事で良いことやっているつもりだけど改善しないという人もいるでしょう。
そのような時、打開策はないものでしょうか。世界には食事療法にもいろいろあり、それぞれ違う食事の診断方法と取り組み方があります。
自分の食事のどこが良いか悪いかを、今と別の見方に変えて見直してみると気づくことがあるかもしれません。そのようなことで気づき一つ食物を改善しただけで、症状がみるみる改善した例があります。
【良し悪しでなく薬膳のように食で病気を治そうとする考えがある。】
食事療法には、日本にも世界にもいろいろあります。その一つに、中国伝統医薬学の食療法(薬膳)があります。
薬膳が発展するまでをみて、食物で健康を取り戻そうとする考え方や方法があることを知りましょう。
最も古い食療法の記述は、唐(618~907)の時代、薬王の孫が書いた医学書「備急千金要方」(びきゅうせんきんようほう)に羊・豚・兎の肝臓・胆等を利用して、眼の病気を治療する方法が載っています。現代西洋医学で言うとビタミンAが効くということかもしれません。
同書の「食治篇」には、食物を野菜・果物・穀類・鳥獣虫魚の4つに分類して、それらを使った治し方が載っています。
孫の弟子孟詵は、上記「食治篇」に食材と中薬を増補し、138種の薬膳の処方を編集して初めての食療法の専門書「食療本草」を書きました。
唐の時代、鑑真和上が日本からの熱心な要望を受け、5度の失敗と失明の上来日し、仏教と医学を伝授しました。日本では、奈良時代のことです。
現代人は、何でも薬・病院に頼ることを前ブログにも書きました。
宋の時代(960~1279)に書かれた陳直の「奉親養老書」には、薬を使っても食物をうまく使って治す人には及ばない、という主旨のことが書かれています。
中国最初の中医薬膳学の専門書「飲膳正要」が、金・元時代(1115~1368)に、宮廷医師の忽思慧によって書かれました。
この中で、「飲食五味は五臓を調和する。五臓のバランスが良くなれば、気血(体をめぐる気と血を言う)が充実し精神が元気になる。情緒が安定するため、風邪のように病気の原因になるものが体内に侵入できないので健康になる。」と書かれています。
※五味とは、酸味・甘味・苦味・辛味・鹹味(塩味)のこと
※五臓とは、人体の臓器、肝・心・脾・肺・腎のこと
上記のように、病気を予防し健康を保つためには飲食は大事であるとし、スープ・粥等の多くの料理も紹介しています。
1368~1644の明の時代には薬膳学・中医薬学が発展し、成熟期に入り、有名な李時珍によって「本草綱目」が書かれました。
内容は、食材と中薬を水部・穀部・菜部・菓部・禽部・獣部などに分け、薬・方剤・食薬を使った粥・薬酒等1万以上を載せています。
その中に、食材を用いて病気を治療することと薬膳の内容が多く書かれています。
1644~1912の清の時代に曹慈山が書いた「老老恒言」には、老人のための薬粥100種が書かれています。
また、発熱や発疹・赤痢などの伝染病に関する学問や温病学説が発展しました。
※薬粥は日本の禅寺の健康食になった。
このように、リウマチ膠原病にこの食品は良いか悪いかから一歩踏み出した考え方を持った食事療法があります。
【日本にも世界にもいろいろな食の見方が違う食事療法があります。】
アーユルベーダや国内にもいろいろあります。西洋医学の栄養学もあります。
【悪い食事ではないと思うが、いまいちの時は別の食事療法の見方をしてみる。】
当食事のアンケートを見ても、本人も当方もあまり悪い食事ではないが、いまいちリウマチ膠原病が改善しない時があります。食事だけが発症原因ではないですが、そんな時は今やっている食事療法以外の食事療法の見方からみて、食事の良し悪しが発見できることがあります。
以前、山田まりやさんの本のことをブログで書いたことがあります。何ヶ月かヒマができた山田さんは、マクロビオテックと薬膳を一緒に勉強したのでした。すると、似ているようで違っていることに気づいたようです。
例えば、食物等の陰性陽性の判断が一部違っています。診断の結果が少し違います。したがって、対応策が変わることがあります。
そのようなことがありますので、別の食事療法で観るとヒントになることがあります。
私の例でも、患者の方の現在状況からリウマチが治るはずだと思うのに、何故だろうと思った時、何か他に食べてませんかと言ったら、その患者の方は今まで言ってなかった陰性の食物を思い出し、毎日食べてますと言ったのです。
それを、私は最終的に東洋医学の陰陽等ではなくて、西洋医学のデータに照らし合わせて判断しますと、やはり良くないと判断してその食物を止めてもらったらみるみる好転しました。
また、別の膠原病の方で食のかたよりが一目で分かったので、海藻くらい食べてみませんか、と特に意味もなくつぶやいたのですが、その後、「めかぶ」を食されアトピーが良くなったとことがあります。栄養不足(葉酸)だったかもしれません。
また、食物に対する考え方・食の良い悪い・病気を治すためや体質改善のためと、いろいろな食事療法によって目的・考え方・方法が違うので、違うことをやるのも一つの改善方法です。
安 靖(あんせい)
〒815-0032 福岡市南区塩原3-1-23-105
☎ 092-511-3234
HPのURL
https://ryumachi.ansei-support.com/
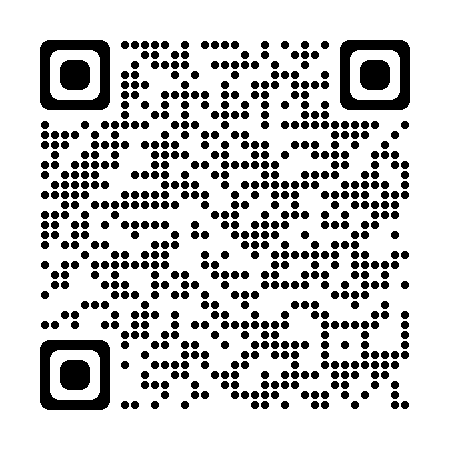
「日本の食物史からのヒント」PARTⅠ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku1/
「日本の食物史からのヒント」PARTⅡ
https://ryumachi.ansei-support.com/kansen-syoku2/
ご相談・お申し込みはこちらへ
https://ryumachi.ansei-support.com/soudan
◆24時間メール受付 メール(終日)
E-mail hzw03430@nifty.ne.jp
Posted by ansei at 09:39│Comments(0)

